
イチオシポイント



保育・教育の特徴
主体性を育む異年齢児保育・選択性保育
活動や目的に応じたより自由な異年齢児保育、自分で好きな遊びや場所を選べる選択制保育を実践
働きがい
保育にも行事にも「余白」を
日々の遊びや行事はすべて決めてしまわずに、子どもと保育者のやり取りを通して創り上げます
働きやすさ
「働きやすい職場」の認定を多数受賞
チーム保育だから休みが取りやすい◎特別休暇あり、年間休日122日、ノンコンタクトタイム導入
入社後支援・研修
若手もどんどんアイデアを出せる
定期面談・充実の研修あり◎ピアノは苦手でもOK!あなたの好きなことを活かして楽しく保育♪
理念



理念
『共生と共学』
社会で個を育み、個が社会と繋がっていく
方針・目標
方針
『 子ども主体の保育の創造』
・体育
体を十分に動かし、健やかな心身の発達を促す
・徳育
人としての大切な心情を育む
・共育
人間関係向上のための5つの関係性を育む
子どもと親、子どもと保育者、子どもと子ども、保育者と親、子どもと地域
目標
・自立と自律
自分で選択し、自分で行動できる子ども
・コミュニケーション能力の向上
人の話を聞き、自分の考えを素直に表現できる子ども
・多様性の尊重
人の気持ちをわかろうとし、人に喜ばれることを自分の喜びとすることができる子ども
方法
・たてわりではない異年齢児保育
・子ども主体の保育
・ねらいに応じた選択性の保育
・かかわりを大切にした保育
・職員によるチーム保育
これらの方法に基づき行う保育を「見守る保育」と言います。「見守る保育」とは、卒園までに見守っても大丈夫な子どもたちを育てる保育のことを言います。
保育者としての信念(三省)
『子どもの存在を丸ごと信じただろうか』
私たちは、子どもの自ら育とうとする力を信じます
私たちは、子どものすべての行動に意味があると信じます
『子ども主体の保育』
私たちは、子どもの気持ちを受容し、尊重し、しっかりと向き合います
私たちは、子どもの声に耳を傾け、内面的な思いにも寄り添います
『ねらいに応じた選択性の保育』
私たちは、子どもの意欲・好奇心・探求心を支えます
私たちは、子どもの育ちの邪魔をしません
目指す子ども像
・自分で選択し、自分で行動できる子ども
・人の話を聞き、自分の考えを素直に表現できる子ども
・人の気持ちをわかろうとし、人に喜ばれることを自分の喜びとすることができる子ども
法人概要
| 法人名 | 社会福祉法人 正道会 |
|---|---|
| 法人住所 | 長崎県長崎市かき道3-1-11 |
| 設立年 | 1999年7月 |
| 事業内容 | 保育園・こども園・学童クラブ・児童発達支援施設・放課後等デイサービス・病児保育室・子育て支援拠点施設などの運営 |
| 施設数 | 28施設 |
| 従業員数 | 約350名 |
| 特記事項 | ▼公式ホームページはこちら 社会福祉法人 正道会|公式ホームページ 社会福祉法人 正道会|採用ホームページ ▼公式Instagramはこちら 社会福祉法人 正道会 関東|Instagram 社会福祉法人 正道会 福岡|Instagram ▼公式facebookはこちら 社会福祉法人 正道会|facebook ▼公式LINEはこちら 社会福祉法人 正道会|LINE |
園紹介インタビュー
-

-
南畑ピノキオ森のこども園 園長 上戸 雄太
「自分らしさ」と、自分らしさから生まれる
「私たちらしさ」を大切にしている園です。
どんな保育・教育をしていますか?
私たちは『子ども主体の保育の創造』を大きな方針として掲げ、「見守る保育」を日々実践しています。私たちが考える「見守る保育」とは、卒園までに見守っても大丈夫な子どもたちを育てることです。そのために、縦割りではない、より柔軟な異年齢児保育や、ねらいに応じた選択性保育など独自の取り組みで、子ども自身が好きな遊び・好きな人・好きな場所を選び遊び込める環境を作っています。そしてそんな柔軟な保育を支えているのが、職員たちの抜群のチームワークです。
園で過ごす子どもたちの様子は?
普段から異年齢で生活しているので、小さな子にも自然と関われる子どもたちです。先日は「わいわい避難訓練」という子どもたち主体で行う不審者対応避難訓練を実施しました。当日の先生たちはあくまで伴走者。不審者役の先生を発見すると、年長さんが小さな子たちを手分けして誘導してくれました。なるべく小声で呼びかけたり、不安そうな子をあやしたり。先生の姿をとてもよく観察していることや、子どもの持つ力を感じられ、思わず先生たちの目には涙があふれました。
園で働く人たちの様子は?
30~40代が中心で、何事にも主体的・積極的な先生方です。子どもたちの未来や保育の在り方についてとことん追求したい!という気持ちがあり、それぞれが納得いくまで質問や意見を交わし合っています。そんな時間を過ごしているからこそ生まれるチームワークには、目を見張るものがありますよ。また、各々が得意なことを活かしているので、ピアノ以外にもギターやハーモニカ、時には手拍子とアカペラなど、みんな思い思いに音楽を楽しむ姿もとても素敵なんです。
どんな園にしていきたいですか?
正道会は、今までそうしてきたからと過去に捉われることなく、広い視野でこれからを見据えられる法人だと感じています。だからこそ、子どもが主役であると同時に職員も主役であると考え、先生たちの「やってみたい」を法人として後押ししています。ここではみんなが積極的に挑戦でき、主体的でいられるんです。これからも先生たちの活発な意見を聞きながら、ICTや様々な先進的な保育なども、初めから否定せず前向きに検討した上で導入を判断していきたいと思っています。
園見学で見てほしいところは?
おすすめは午前中の活動の見学です。子どもと保育者の距離感や、保育者同士のリアルなやりとりがじっくり見られますよ。遊び場をコーナー分けしていることで、目的を持ってその場所で過ごす子どもたちの姿や、トラブルが起きても互いに折り合いをつけ自分たちで解決する姿などにもぜひ注目してください。地域の方々との交流も多いので、とても人懐っこいですよ。説明の際には「聞きにくいこともこっそり聞いてOKだよ」のコーナーを設け、思い切った質問もあり好評です!
学生へのメッセージをお願いします!
私は、養成校の先生から「あなたに合っていると思うよ」と勧められ、家からも近かったので正道会に就職しました。そして、同僚の先生たちに保育の楽しさに気づかせてもらいました。養成校の先生の言葉は、人生のターニングポイントとなるありがたい助言でした。みんなで決めて、保育を創り上げていけることが私のやりがいです。みなさんも、最後は自分の意思で決めることを大切にしてください。そうすれば就活や仕事で躓いたとき、自分自身で乗り越える力が湧いてきますよ。
主活動の一例

乳児は月齢によって発達の差が著しい時期なので、一人ひとりに応じた生活リズムや活動を大切にしています。幼児になると、縦割りではない柔軟な異年齢児保育になり、そのときの活動や目的に応じてグループを作ります。日々の遊びには、何をするか、どんな順番でするかを子どもたち自身が選べる選択性の活動を取り入れていきます。時にはクラスではなく習熟度別に活動を行い、適切な指導や子ども同士のより活発な関わりを生んでいます。毎週末に今週の子どもたちの姿を振り返り翌週のスケジュールを決めていますが、子どもたちの興味・関心を大切にしているので、当日の活動は柔軟に変更できます。子どもと保育者がやりとりをしながら保育を創り上げていけるよう、「余白」を大切にしています。
1日の流れの一例

| 7:00 | 7:00 開園/順次登園/視診・検温 合同自由遊び(異年齢での関わりのゴールデンタイム) |
|---|---|
| 8:00 | 8:15 以上児・未満児のお部屋に分かれて保育 |
| 9:00 | 9:30 朝おやつ・水分補給 |
| 10:00 | 10:00 主活動 |
| 11:00 | 11:00 着替え・オムツ交換・排泄など 11:30 昼食(離乳食から順次) |
| 12:00 | 12:30 午睡(年齢によって時間は前後します) |
| 15:00 | 15:00 起床/おやつ |
| 16:00 | 16:00 自由遊び(異年齢での関わりのゴールデンタイム) 順次降園 |
| 19:00 | 19:00 閉園 |
| 7:00 | 7:00 開園/順次登園/視診・検温 合同自由遊び(異年齢での関わりのゴールデンタイム) |
|---|---|
| 8:00 | 8:15 以上児・未満児のお部屋に分かれて保育 |
| 9:00 | 9:30 お集り |
| 10:00 | 10:00 主活動(課題別保育)/着替えオムツ交換・排泄など ※クラス活動・選択性活動・選択順序性活動・習熟度別活動 |
| 12:00 | 12:00 昼食 月に1度は“わいわいごはん”(離乳後の子から全クラス一緒に食事) |
| 13:00 | 13:00 午睡(年齢によって時間は前後します) 午睡が必要ない場合は自由遊び |
| 15:00 | 15:00 起床/おやつ 15:45 お集り |
| 16:00 | 16:00 自由遊び(異年齢での関わりのゴールデンタイム) 順次降園 |
| 19:00 | 19:00 閉園 |
行事の一例

以上児・未満児それぞれのお楽しみ会
行事はゴールではなく「プロセス」だと私たちは考えています。子どもたちは日々の発見や面白い遊びを、まずは身近なお友だちや先生に共有します。そして、家族のみんなにも伝えたいという気持ちが芽生えます。そこで家族を園に招待するにはどのような準備をしたらいいか、保育者と子どもたちが一緒に考える…そんな一連の流れの中に行事があります。先生たちは子どもの声を聞いて舵を取りますが、たとえば劇でも配役や立ち位置、セリフは決めすぎないようにします。日々の保育と同じように「余白」を作り、子どもたちの自由な発想から生まれるものを大切にしています。当日は、保護者の方も重要な登場人物。緊張している子には声援を送っていただいたり、時にはハイタッチしたり。企画から実行まで、園に関わるみんなでお楽しみ会を創り上げています。
| 4月 | 入園式/歓迎遠足/健康診断 |
|---|---|
| 5月 | こどもの日の集い/歯科健診/尿検査/田植え体験(5歳児) |
| 6月 | 保護者個人面談/保育参観 |
| 7月 | プール開き/七夕の集い/お泊まり保育(5歳児) |
| 8月 | 夕涼み会/消防総合訓練 |
| 9月 | 敬老の日の集い |
| 10月 | ふれあい運動会/健康診断/稲刈り(5歳児) |
| 11月 | 保育参加/收穫遠足(3~5歳児) |
| 12月 | もちつき会/クリスマス会/新幹線乗車体験(4・5歳児) |
| 1月 | お汁粉会/出初式見学(5歳児) |
| 2月 | 節分の集い(豆まき)/お楽しみ会 |
| 3月 | ひな祭り会/思い出遠足(5歳児)/お別れ会/卒園式(5歳児) |
◆その他の活動:運動タイム(適時4・5歳児、内部講師)/英語であそぼう/リトミック/姉妹園交流/園外活動 など
※上記は南畑ピノキオ森のこども園の例です。
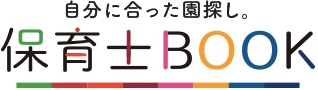
 無料相談
無料相談 資料請求
資料請求 見学申込
見学申込