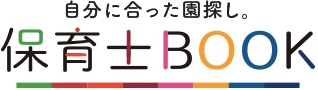ジャーナル
2020.05.06保育園レポート
株式会社モード・プランニング・ジャパン|食べることは生きる力!子ども・職員・保護者 みんな輝く保育園へ

「輝く大人が輝く子どもと子どもの未来を育てる」がコンセプトの雲母保育園。首都圏を中心に展開しています。
特に食育に力を入れているのだとか。園長先生と管理栄養士さん、保育士さんたちにお話しを伺いました。
雲母保育園では特に食育に力を入れていらっしゃいますよね?
 子どもたちにとって食べることは生きる力、生きる軸になります。きちんとよく噛んで食べて、よく寝る。あたり前の生活が、情報過多の現代においては意外と疎かになっていると感じています。そこで雲母保育園では食育を通じて学べることが多いと考えて、保育士と管理栄養士が協力し、子どもたちの栄養をしっかりと考えた献立を提供しています。園では市販のお菓子は出しません。おやつは手作りで、給食は野菜を多く取り入れたメニューが中心です。食物繊維が多い献立が功を奏したのか、子どもたちの便秘が減りました。また0・1・2歳児の朝のおやつは蒸したスティック野菜と牛乳です。今ではそれが習慣になっているので、乳児たちは好き嫌いなく野菜を食べます。幼児クラスで野菜を食べたくない子どもが立ち歩いてしまったら、食事は片付けます。子どもには、今食べるものはこれしかないと理解させることも必要なので。お腹が空けば野菜も食べるでしょう。これが食育の考え方です。
子どもたちにとって食べることは生きる力、生きる軸になります。きちんとよく噛んで食べて、よく寝る。あたり前の生活が、情報過多の現代においては意外と疎かになっていると感じています。そこで雲母保育園では食育を通じて学べることが多いと考えて、保育士と管理栄養士が協力し、子どもたちの栄養をしっかりと考えた献立を提供しています。園では市販のお菓子は出しません。おやつは手作りで、給食は野菜を多く取り入れたメニューが中心です。食物繊維が多い献立が功を奏したのか、子どもたちの便秘が減りました。また0・1・2歳児の朝のおやつは蒸したスティック野菜と牛乳です。今ではそれが習慣になっているので、乳児たちは好き嫌いなく野菜を食べます。幼児クラスで野菜を食べたくない子どもが立ち歩いてしまったら、食事は片付けます。子どもには、今食べるものはこれしかないと理解させることも必要なので。お腹が空けば野菜も食べるでしょう。これが食育の考え方です。
栄養士さんはどんな役割を担っていますか?
 管理栄養士が園長先生と保育士さんと協力して保育に携わっています。主に食育に関することですが他法人の園では保育士は保育、栄養士は調理とハッキリ仕事に線引きがありました。ここではそれがなく、より深く子どもたちに関わることができて、やりがいを感じています。職員同士のコミュニケーションも良好で、働きやすいです。偏食が激しくてほとんど食べなかった子に根気強く接することで、半分くらいは食べられるようになったり、私の名前を覚えてくれて、声をかけてくれる子もいます。毎日子どもたちの「美味しかったよ」という言葉と、空のお皿を見ることが嬉しくて。本当に楽しく充実した日々です。グループ園全園で年に2回行う給食フェアのイベントも励みになっています。
管理栄養士が園長先生と保育士さんと協力して保育に携わっています。主に食育に関することですが他法人の園では保育士は保育、栄養士は調理とハッキリ仕事に線引きがありました。ここではそれがなく、より深く子どもたちに関わることができて、やりがいを感じています。職員同士のコミュニケーションも良好で、働きやすいです。偏食が激しくてほとんど食べなかった子に根気強く接することで、半分くらいは食べられるようになったり、私の名前を覚えてくれて、声をかけてくれる子もいます。毎日子どもたちの「美味しかったよ」という言葉と、空のお皿を見ることが嬉しくて。本当に楽しく充実した日々です。グループ園全園で年に2回行う給食フェアのイベントも励みになっています。
雲母保育園で大事にしている保育観を事業部長に伺いました。
 例えば子どもが転んだ時、保育士は飛んで行って「痛かったね」と慰めるようなイメージがあります。共感的理解は大事ですが、子どもの自立を目指す保育を実践する時、立ち止まって考えるよう指導します。やり過ぎて甘やかしになると、子ども自身が立ち上がる機会を奪ってしまうからです。また子どもたちとは別れが前提の出会いだと教えていて、距離を置いたらどうかな!?と伝えます。卒園しても活躍できる子を育むのが雲母の保育だと考えています。学生さんには見学で現場を感じて欲しいです。
例えば子どもが転んだ時、保育士は飛んで行って「痛かったね」と慰めるようなイメージがあります。共感的理解は大事ですが、子どもの自立を目指す保育を実践する時、立ち止まって考えるよう指導します。やり過ぎて甘やかしになると、子ども自身が立ち上がる機会を奪ってしまうからです。また子どもたちとは別れが前提の出会いだと教えていて、距離を置いたらどうかな!?と伝えます。卒園しても活躍できる子を育むのが雲母の保育だと考えています。学生さんには見学で現場を感じて欲しいです。
センパイ保育士さんインタビュー!

雲母保育園ってどんな保育園?働いてみてどうですか?
雲母保育園は、子どもの自立を大切にしています。きらら教室などの幼児教育もあり食育に力を入れてます。働いてみて休みがとりやすいと感じてます。
入社して感じたのは、新園なので保育に関しても自由度が高く、園長先生が保育士の意見を取り入れてくれるので働きやすいです!
学生の皆さんへメッセージ!
園長先生の教えですが、失敗と書いてケイケンと読む。最初は失敗して当たり前。経験を積めば必ず成長しますのでめげないで!
保育園の職場環境は様々。園見学をいっぱいして自分に合う保育園を選んでほしい。
採用担当さんからひとこと
 雲母保育園では、子ども達、保護者、職員みんなが輝ける園を目指し、保育士さんが働きやすい環境づくりを進めています。
プライベートを重視したい方、ぜひ見学にお越しください。
株式会社モード・プランニング・ジャパンの保育園
相模大野雲母保育園はこちら
雲母保育園では、子ども達、保護者、職員みんなが輝ける園を目指し、保育士さんが働きやすい環境づくりを進めています。
プライベートを重視したい方、ぜひ見学にお越しください。
株式会社モード・プランニング・ジャパンの保育園
相模大野雲母保育園はこちら